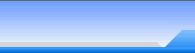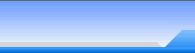| ��)1 |
�����@� ���a23�N���� |
| ��)2 |
��q�������w�j�z�͖@�A�×{��a32�N����� ����{����w�p������ģ
���a47�N |
| ��)3 |
��z�͖@�w�j(����)����Ȏ��R�ی��/ P.1 �i����14�N3���j |
| ��)4 |
��������R�ی�ǒ��ʒm/���{����� ���a57�N5��25�� |
| ��)5 |
�����K�g�(��)���{����� ���ȊďC�@P.115�`P.116��� |
| ��)6 |
������wBalneology��z�[���y�[�W/�Q�n��w��w���t���a�@�����@ |
| ��)7 |
��Ȃ�����͑̂ɂ����̂�����{����Ȋw����J�V���|�W�E������
P.1�`P.6�@/����Ö@��:�ؕ�����v�i2000.8.25�j |
| ��)8 |
�����̈�w��i�u�k�Ќ���V��1423�j�ѓ��T�꒘�i1998.10�j |
| ��)9 |
��������/����14�N�x�t�G���ʓW�}�^�����W��`���̉���̃��b�Z�[�W�`
P.40�`P.44/�������٥�F�̉�i2002.4.26�j |
| ��)10 |
������V��/�ƒ뗓/�}�C�w���X����{���N�J�����c�F��t�A�c���F�i1996.6.1�j |
| ��)11 |
�⑫
����Ö@���Ȋw�I�����Ɋ�Â�����Âł��邽�߂ɂ́A���̍������J�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������A�Ȋw�I���ؖ@�i��d�ӌ���r�@�Ȃǁj�������p��������Ö@�ɓK�p���鎖�͌����I�ɂ͕s�\�ł���B
���̂悤�ȏ̒��ŁA����{����C����w�ł͉���×{���ʂ̉Ȋw�I���̕K�v������A���P�̍�Ƃ��āA���Ȃ��ϓI�ƂȂ邪�����×{
���ʂ�QOL�iQualityOfLife�j�]����̎��{�ɓ��ݐ��Ă���B |
| ��)12 |
�i���j����������/���� �ØI���חY�i���w���m�j�̒k�b���i2004.7.6�j |
| ��)13 |
�⑫
��ʓI�ȉ���×{�͈㎖�@�E�@�̔��e�ɓ���Ȃ����A����Ö@��̉��ōs�����p�́A��Ís�ׂƂȂ�㎖�@�̔��e�ƂȂ�B |